
【パナソニック住宅用防災警報器けむり当番2種電池交換】
今回は防災警報器 以下、火災報知器の電池交換についての記事になります。
目次
防災警告器の場所特定と外し方
早いもので新築してからもう10年、いろいろなものに故障やガタが見え始めます。
ある夜家に帰ると「ピッ、電池切れです」とどこからか機械の声が聞こえてきます、ん?
それが連続して聞こえず、1時間に1回。
どこで鳴っているのか特定するのにのに3.4回聞きました。

基本的に高い位置に取り付けられているので、
取り外し時には踏み台など安全な物の上で作業することをお勧めします。
電池切れお知らせ音を止めるには、警報停止ボタンを押す、または引きひもを引きましょう。
本体を上に少し押しながら左(時計と反対周り)回すと簡単に外れます。
専用リチウム電池の交換方法
電池コネクタからコネクタを引っ張って外します
そして新しい専用リチウム電池を差し込みます
動作確認のため警報停止ボタンまたは引きひもを1秒間ほど引きます
動作灯が3回点滅と同時に「ピッ、正常です」と1回なれば正常です
ちなみにですが、新しい電池が届くあいだ一度抜いたリチウム電池を差しても「ピッ、電池切れです」
がしばらく鳴らなかったので、いつまた鳴るのか気になってそのままにして 早2ヶ月
未だに「ピッ、電池切れです」は鳴っていません。
火災報知器設置義務化
2004年に消防法の改正がおこなわれ、
戸建てを含めたすべての住宅において住宅用火災報知器を設置することが義務となりました。
2006年6月に新築住宅への設置が義務化され、
既存住宅も順次義務化が進み、2011年6月までには全国すべての住宅が対象になりました。
義務化されているとはいえ、取り付けなかったとしても罰則が発生するわけではありません。
我が家の火災報知器SHK38455の後継機が出ています
設置が義務付られている場所
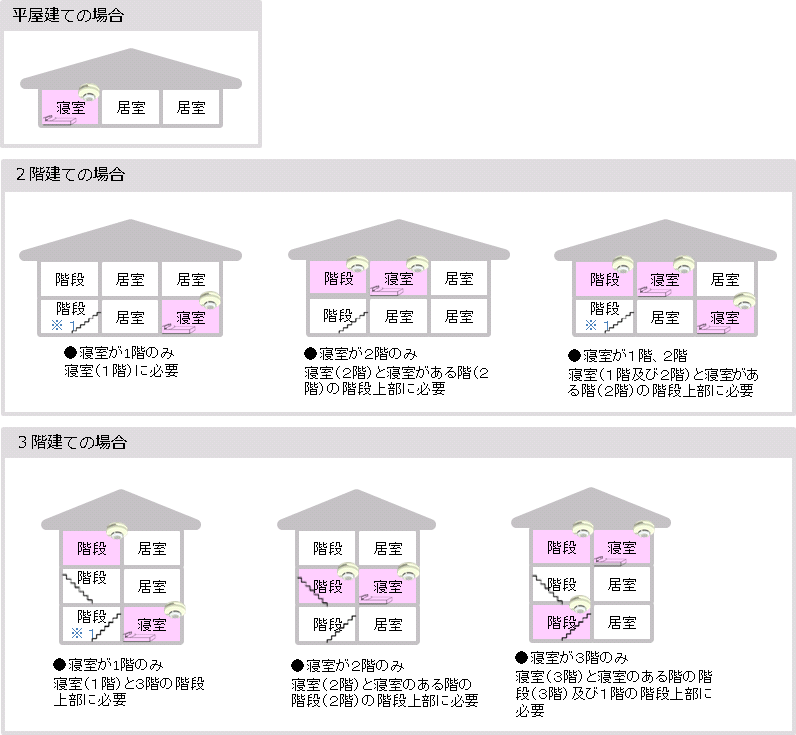
画像引用 消防庁 住宅用火災警報器Q&A
※1 この場合、1回の階段には設置不要
1階建て(平屋)の場合は、階段がないため寝室のみになっています。
2階建ての場合は、寝室と階段への設置が必要です。2階にも寝室がある住宅なら、1階から2階へ続く階段の上部にも火災警報器が必要です。
ただし、寝室が1階のみの場合は、階段への取り付けは無しで大丈夫です。
3階建ての場合も、寝室と階段への設置が必要で。寝室が2階や3階にある場合は、その階の階段上部に火災警報器を取り付けてください。
なお、寝室が1階のみの場合でも、3階の階段上部には取り付けが必要になります。さらに、寝室が3階のみの場合は、3階だけでなく1階の階段にも火災警報器を取り付ける必要があります。

その他の条件については自治体によって違うようです、詳細については、お住まいの自治体のホームページをご確認ください。
設置が義務付けられていない場所
自動火災報知設備が既に設置されている場所や、スプリンクラーがある場所などは取り付けなくてもいいようです。
ただし、基本的に自動火災報知設備が設置されているのはマンションの廊下などの共用エリアとなっています。もし専有(住宅)エリアに設置されていなければ取り付けが必要になります。また、戸建てに住む方はご自身で用意する必要があります。
また、自治体によっては設置義務がない場所もあります。詳細については、お住まいの自治体のホームページをご確認ください。
お手入れと定期点検
メーカーの説明書によると6ヶ月に1回以上の定期点検をおこなってくださいとのこと
煙検知部のホコリや汚れを確認して、
水または石鹸水に布を浸しよく絞って汚れやホコリを取って下さい。
動作確認もしておくといいでしょう。
注意点したいこと
火災報知機を止めたまま放置や、電池交換だけ行うのはおすすめできません。
火災警報器は約10年で電池寿命となる上、回路やセンサに不具合が出てくる恐れがあるため、
本体ごと交換が消防庁や日本火災報知機工業会で推奨されています。

持家の一戸建てにお住まいの方は、基本的に火災警報器の交換判断をご自身で行う必要があります。
新しい火災警報器をご自身で選んで購入しましょう。
元々設置されていたものから、別のメーカーに変更してもOKです。
いつも参考にさせてもらってますPanasonic.bizのリンクを貼っておきます
付けてみたい火災報知器
一酸化炭素検知機能付きの火災警報器 「プラシオ」
ドライバー1本で誰でもかんたんに取り付けられます。
壁に設置する場合は、ドライバーも不要で石膏ボード用ピンで取り付けが可能です。
法令上の設置場所については以下の通りです
あとがき
火災報知器とは火災により 発生する煙を感知して、音や音声で警報を出すもののことです。
その家の住人が火災から逃げ遅れることを防ぐためのものです。
今回初めて電池交換や本体交換をするにあたりネットなどで調べてみましたが
簡単そうに見えても年配の方や身体的に不自由な方など危険なのではないかと感じました。
私を含めですが安全第一で作業することを考えて行った方がいいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。